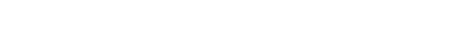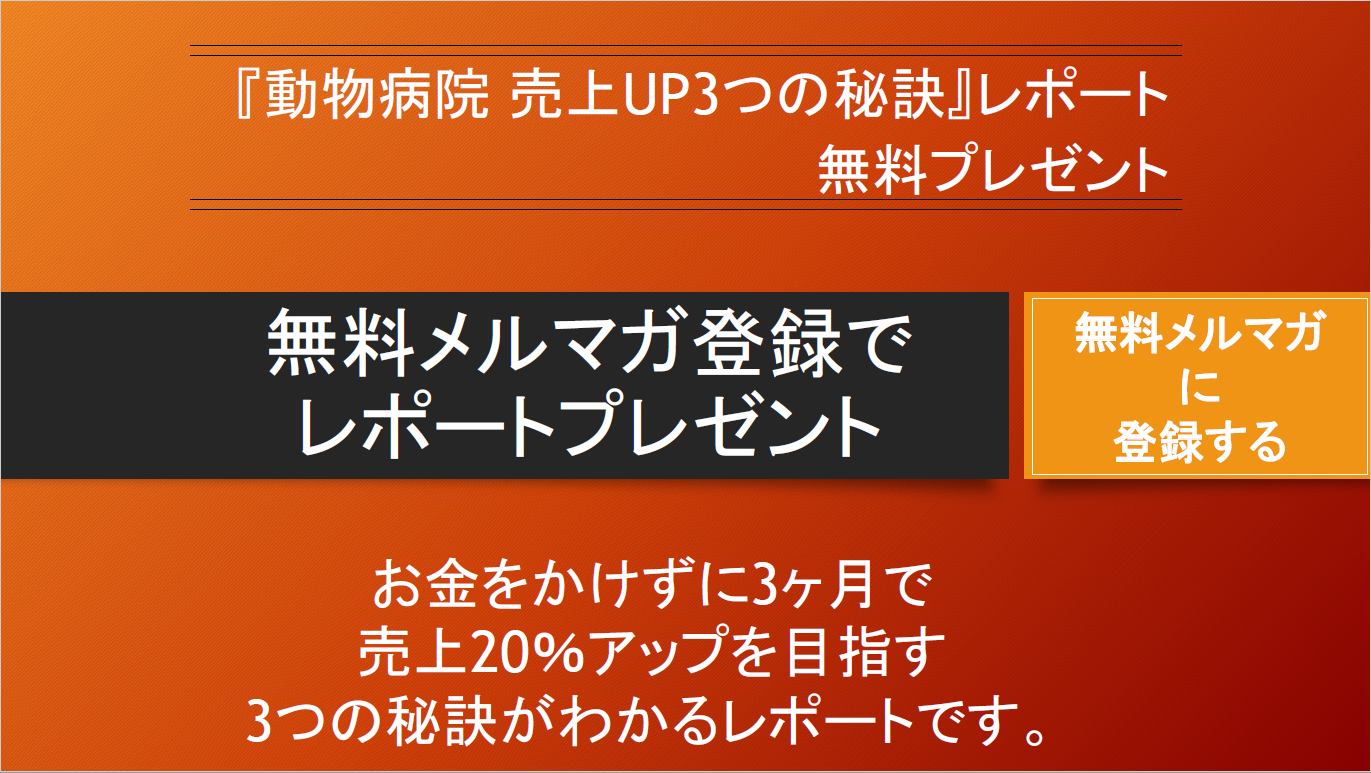「新しい医療機器を導入したものの、あまり使われていない」「高額な費用をかけてWebサイトを作ったにもかかわらず、集客につながっていない」。 動物病院の経営者であれば、このような経験をした覚えが一度はあるのではないでしょうか。
「せっかく費用をかけたんだから、なんとか使わなきゃ…」。そう考えて、過去の投資にいつまでも縛られてしまうことがありますが、これは「サンクコスト(埋没費用)の罠」と呼ばれるものです。 今回は、このサンクコストの正体と、それに振り回されずに冷静な判断を下すための考え方について紹介します。
基本的にネガティブな印象が強いサンクコストですが、あえてその存在を活かす方法もあります。それについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:「やるしかない状況」が経営者を成長させる
サンクコストとは?

サンク(=sunk)とは、sink(=沈む)の過去形。すなわちサンクコストは、「沈んでしまった費用」を意味し、その名の通り戻ってこない資金のことを言います。集客効果が見られなかった広告費用、赤字に終わってしまったキャンペーン費用、また動物病院であれば使わなかった治療機器代はサンクコストの代表例です。サンクコストを一度も出したことがない企業は、ほぼ存在しません。しかし、サンクコストをサンクコストと認めずに、いつまでも執着している企業は少なくないと聞きます。
なぜなのでしょうか。その主な理由として、
- これから良くなるかもしれないと期待してしまう
- ここまで費用をかけたのに途中で辞めたら意味がなくなってしまう
- 自分のプライドを傷つけたくない
の3つが挙げられます。
なぜ人はサンクコストに固執してしまうのでしょうか。その背景には、「コンコルド効果」と呼ばれる心理的バイアスが潜んでいます。これは、投資したコストを惜しむあまり、将来的な損失が明白でも、その事業や計画を継続してしまう心理傾向のことです。
かつて英仏が共同で開発した超音波旅客機コンコルドは、莫大な開発費用と時間をかけたにも関わらず、コストを回収できずに倒産しました。経営陣は、膨大な損失を認識しながらも、「ここまで費用をかけたのだから」という理由でプロジェクトを継続してしまったのです。
このコンコルド効果は、動物病院経営でも起こり得ます。
- 思うように機能しないレセコン(レセプトコンピューター)を、修理やバージョンアップを繰り返しながら使い続ける
- スタッフのスキルアップにつながらない高額な研修を、費用を理由に継続させる
- ほとんど活用していないWebサイトに、維持費を払い続ける
これらはすべて、サンクコストに縛られている状態です。サンクコストへの期待は事業経営だけでなく、ギャンブルや恋愛、株式投資など、日常のさまざまなシーンに潜んでいます。過去の損失にばかり気を取られ、物事の本質を見失わないように注意しましょう。
サンクコストに陥らないためには?
それでは、サンクコストの罠に陥らないためには、どのような心がけをしたら良いのでしょうか。おすすめの3つの方法を紹介します。
①あらかじめ限度を設定しておく
サンクコストの罠にはまらないためには、最初に損切りラインを明確に設定しておくことが最も重要です。キャンペーンや施策を始める前に、必ず予算と期間を決め、それを超えた場合は、たとえ効果がなくても潔く諦めるルールを作りましょう。
例えば、「新しい広告に〇〇円まで投資し、3ヶ月以内に目標の来院者数に達しなければ中止する」といった具体的な指標を設定します。そうすることで、感情に左右されず、冷静な判断を下すことができます。ルールを事前に決めておくことが、あなた自身をサンクコストの執着から守る盾になってくれるでしょう。
撤退条件の決め方については、以下の記事でも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
②客観的な意見を取り入れる

経営者一人では、感情やプライドが邪魔をして、客観的な判断ができなくなることがあります。そんな時、第三者の意見は非常に役立ちます。
信頼できるスタッフをオピニオンリーダーとして決めておくのも良いですが、経営者仲間、税理士、コンサルタントといった、院内の事情に囚われずにアドバイスをくれる専門家を頼るのも有効です。彼らと定期的なミーティングを設定し、施策の進捗や結果について報告・相談する場を設けましょう。一人で抱え込まず、客観的な視点を取り入れることで、損切りラインを徹底でき、より正しい決断ができるようになります。
客観性を得るための方法については、以下の記事で触れていますので、ぜひ合わせてお読みください。
③複数の選択肢を常に持つ
ひとつの施策だけを打ち出していると、ついその施策にこだわってしまいます。これはサンクコストのジレンマに陥りがちなルートです。そのようなことがないように、複数の施策を考えておき、「このキャンペーンがダメだったらこの施策を試す」「コストをAとBとCのプランにそれぞれ3等分する」などとしましょう。確実にひとつの施策への執着がなくなります。
自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする認知の特性を「正常性バイアス」と言います。近年、災害などで注目された言葉であるため、聞いたことがある人も多いでしょう。サンクコストにとらわれていると、いつまで経っても新しい施策が打ち出せず、費用対効果を出すことにも後ろ向きになります。
そのようなことがないように目標設定をする、オピニオンリーダーを置く、複数の施策を考えるなど、いくつかの対策を取りましょう。大切なのはこれまでの損失を嘆くのではなく、失敗を糧に新しいキャンペーンをどんどん試してみることです。トライ&エラーを繰り返していくことで、自分の動物病院に理想的な方向性を見つけられます。