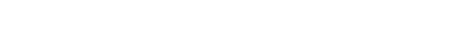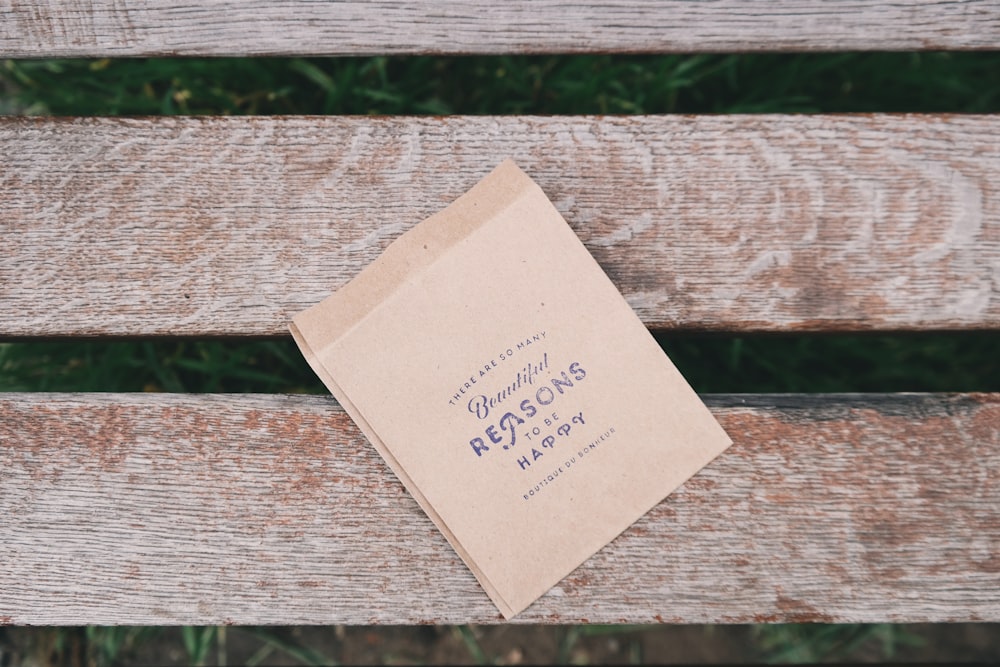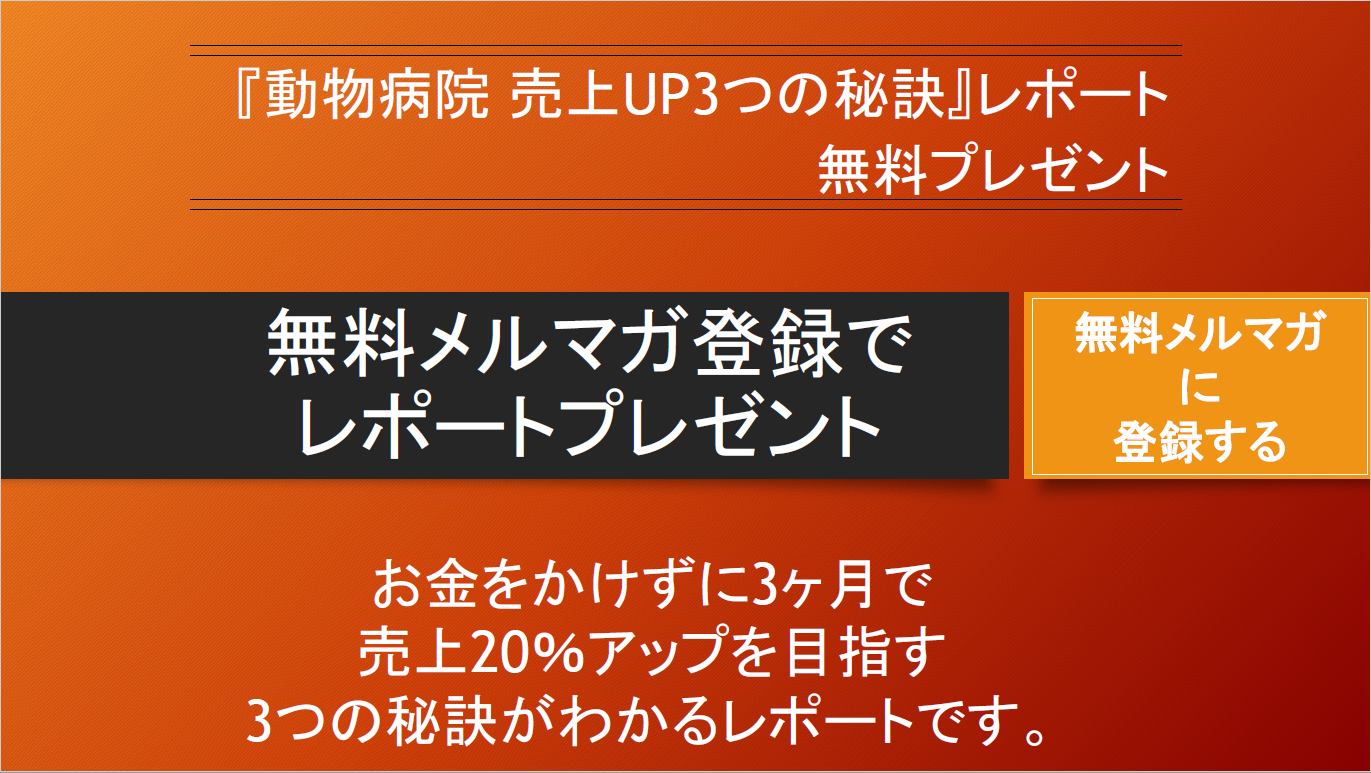新しい商品やサービスなどの施策にどの程度効果があったのかを示す「効果検証」は、動物病院に限らず、すべての企業において重要なフェーズです。
効果検証を行わなければ施策の成否を客観的に判断できず、うまくいっているのに中断してしまったり、反対に採算が取れていないのに継続してロスを出し続けたりするおそれがあるためです。
この効果検証をする際には、成功と失敗の基準となる数値(=KPI)をあらかじめ出しておく必要があります。
なぜこのKPIが必要になるのでしょうか。設定方法についても気になるところです。
今回はKPIの考え方についてお話したいと思います。
KPIを設定する必要性とは
KPIとは「Key Performance Indicator」の頭文字を取ったもので、その名の通り施策の各プロセスのなかで、達成度合いの計測と定量的な評価をするために存在する考え方です。混同されがちな言葉にKGI(Key Goal Indicator)がありますが、これは最終ゴールとなるもので、KPIとは全く異なります。
例えば、「年間売上を前年比120%にする」がKGIなら、「新規来院者数」「リピート率」「平均単価」などがKPIとなります。KPIはKGIを達成するための“中間指標”と考えるとわかりやすく、KPIを考える前にはKGIを設定しておかなければなりません。
その後に、KPIを設定するメリットとしては、主に以下の3つを挙げられます。
目標達成に必要な行動が明確化される
KPIを設定することで、目標を達成するためには具体的に何をしたら良いのかを明確にすることができます。目標を達成している場合はさらなる新しい目標を設定できますし、未達の場合はその原因を究明したり、新しい施策を立てたりして、新しい行動へと移ることができます。
課題の見つけ方については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:動物病院の経営に行き詰まったら課題を見つけて現状を把握しよう
モチベーションの向上
どのような施策でも明確な効果を感じなければ、継続が苦痛になってしまいます。それもKPIを設定し、達成度合いを知ることによってモチベーションを維持しやすくなるはずです。たとえ未達の施策でも新しい施策に切り替えたり、改善策を出し合ったりすることによって、現場の士気は上がっていくでしょう。組織全体の能力向上にもつながっていくはずです。
評価基準を統一できる
客観的な評価基準を設けることによって、組織全体の認識を統一することができます。評価基準を曖昧にしているとスタッフ間に不公平感が生まれやすくなりますが、具体的な数値で成否の線引きをしてあげることで、不平不満は出にくくなるでしょう。同じ目標に向かわせることで競争意識が良い感じに芽生えるようになり、動物病院の売上が改善されていくかもしれません。
動物病院では、よく以下の指標がKPIとして設定される傾向にあります。
・来院数(新規・再診の割合)
・平均診療単価
・再来院率・紹介率
・予約キャンセル率
・スタッフ対応満足度アンケート
これらを数値化して追うことで、施策のどこが効果的か、どこに改善の余地があるかを見極めやすくなるでしょう。
プロセスを見直す大切さについては、以下の記事でも触れていますのでぜひ参考にしてください。
効果検証に役立つKPIの設定方法
KPIの重要性を理解したところで、ここからはKPIの設定方法を考えていきましょう。このときに役立つのは「SMART」という考え方です。5つの要素を明確にすることで、曖昧になっている成功と失敗の基準をきっちりと設けられます。
Specific(明確性)
まずは目標を明確にすることが重要です。「来院者数を増やしたい」というざっくりとした目標ではなく、「〇ヶ月で来院者数を〇人増やす」「売上額を前年比130%にする」といった具体的な目標を設定しましょう。
Measure(測定可能)
成否の基準については必ず数値で定めるようにしてください。数値は誰の目から見ても客観的に判断できる指標であり、達成したときには大きなやりがいが感じられます。反対に抽象的な評価は達成感を感じづらく、不平等が生まれやすくなるため、ビジネスシーンにおいてはおすすめできません。
Achievable(達成可能)
目標は高ければ高いほど良いと思われがちですが、あまりに高すぎる目標は現実感がなく、達成へのモチベーションが上がりにくいものです。少し頑張れば手に届きそうな目標をまずは設定して、徐々にハードルを上げていくと良いでしょう。そのためには目標設定と効果検証を何度も繰り返す必要があります。
Related(関連性)
関連性のない小さな目標をいくつも設定すると、最終的なゴールが見えづらくなります。あなたの最終的な目標はどこにあるのでしょうか。おそらく多くの獣医師が「売上の拡大」を目標に掲げているはずです。それであれば「新商品の開発」「新しい診療サービスの提供」「スタッフの応対改善」など、最終的には売上の拡大につながる細かな目標をいくつも掲げて、それぞれのKPIを設定するようにしてください。
Time-bounded(適時性)
最後の適時性とは、いわゆる目標設定と達成のタイミングのことです。どんなに的確な目標数値を設定したとしても、時期を設定しなければ中だるみしてしまいます。同じ目標でも1ヶ月で達成するのと、1年かけて達成するのではまったく意味も異なります。長すぎない、短かすぎない長さに達成時期を設定しましょう。
今回は効果検証で大きな役割を果たすKPIの設定方法について説明しました。KPIというと難しいイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。今回紹介した「SMART」の考えに基づいたうえで、これまでの経験を参考にした目標設定を行いましょう。あなただけでなく、現場のスタッフと一緒に考え、現場の感覚や課題感を取り入れることで、より現実的で納得感のある数値を設定できます。また、自分たちが関わって決めた目標には、達成への意識も高まりやすくなります。
ただし、KPI設定に失敗例がないわけではありません。
・指標が多すぎて追いきれない
・数値の根拠が曖昧
・達成しても評価されない
これらは典型的なKPI設定の失敗例といえます。KPIは設定して終わりではありません。成功させるためには、「現場で管理・共有できる範囲」に照準を絞り、達成したら必ずフィードバックする仕組みを作りましょう。
定期的にデータを収集し、達成度を確認して改善策を練る「PDCAサイクル」を回せるよう、月次・四半期ごとに振り返りの場を設けると、成果を実感しやすくなります。
最後に振り返りの大切さを解説している記事を紹介しますので、ぜひ合わせてお読みください。