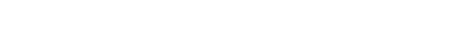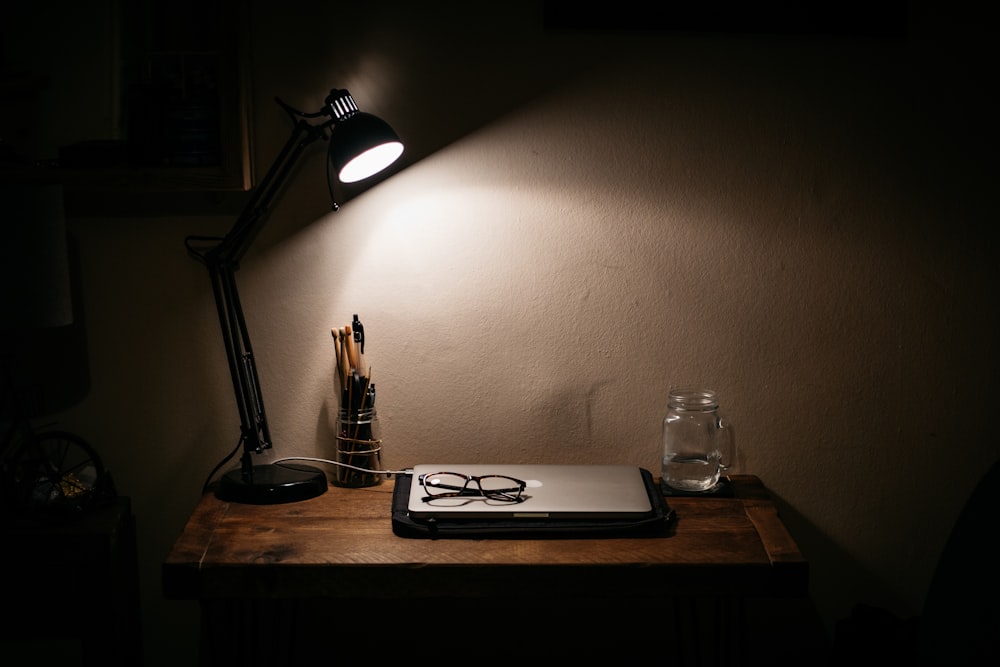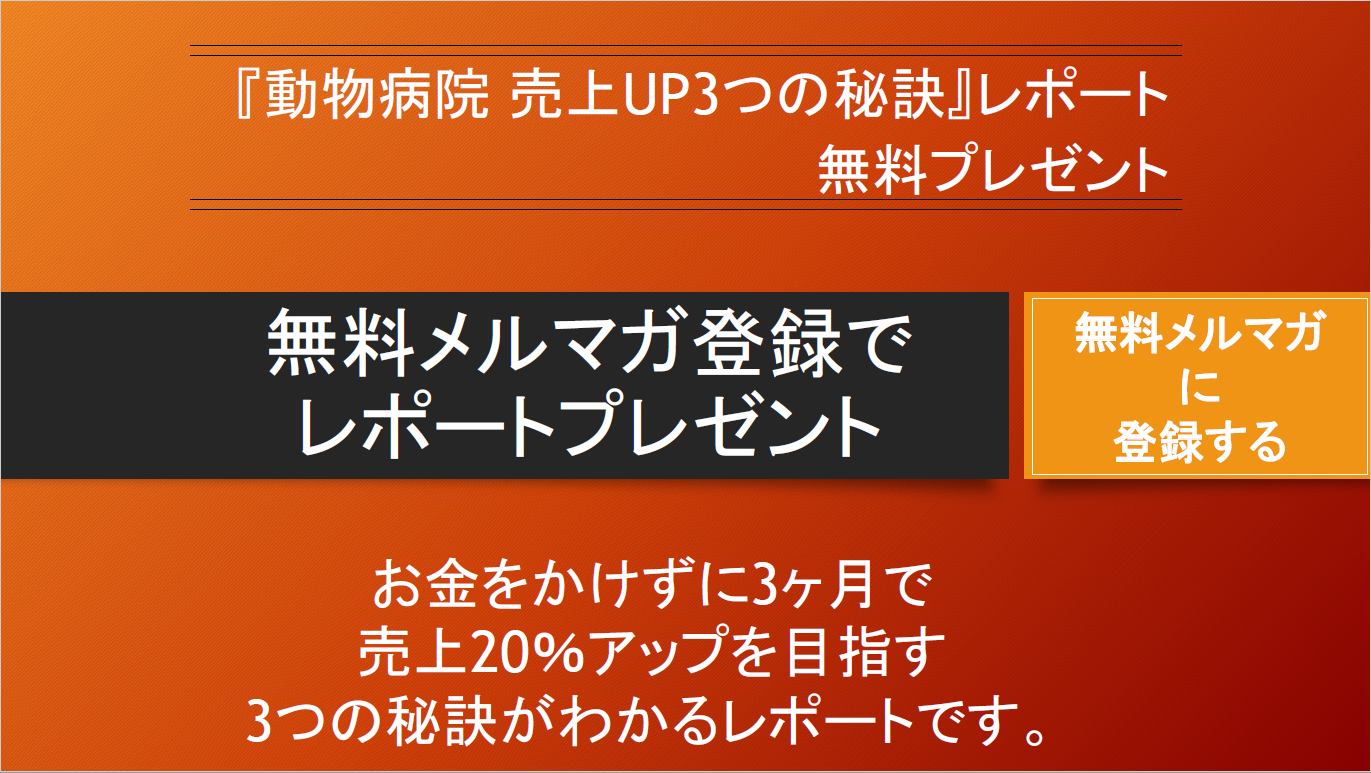2024年の時点で、日本全国には16,000院を超える動物病院が存在することが農林水産省の調査で分かっています。動物病院の数は年々増加傾向にあり、私が開院している市内にも10院以上存在していて、決して競争が激しくない訳ではないです。
しかし、競合他社よりも上に行こうとするだけではなく、ときには味方につけることも大切ではないでしょうか。ライバルを協力者とすることで、今まで気づけなかった自院の弱点に気づけたり、新しい経営者としての視点に気づけたりする可能性があります。
それでは、どのように同業他社を協力者にするべきでしょうか。今回は、実際にあった動物病院の業務提携の事例と、相手を味方につける方法、そのメリットについてお話していきましょう。
参考:農林水産省 飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数)
動物病院で見られる業務提携の事例
動物病院の業務提携に興味はあるものの、具体的に何をどのように行えばいいのかわからないという方は少なくありません。それほど動物病院の業務提携事例は、まだ一般に浸透していない話だと言えます。少しでもイメージができるよう、ここからは動物病院の業務提携の事例を紹介します。
ドッグトレーナーやトリマーとの業務提携
近年のペットブームを受けて、ただ動物を診療するだけではなく、ペットホテルやトリミングなど複数のサービスを展開する動物病院が増加しています。それを行う場合、必要になってくるのが動物のトレーニングやトリミングといった専門的な知識を持つスタッフの確保です。獣医師が積極的にフリーランスのトリマーやドッグトレーナーと業務提携すれば、ひとつの診療所内で複数のサービスを展開することができて、発展を期待できます。
獣医師の独立サポートで業務提携
あなたの動物病院で獣医師を育てる教育体制が整っているようであれば、勤務医や獣医師の資格取得者を対象にした独立支援を行うこともできるでしょう。その獣医師が独立した際に、グループ医院のひとつとして手を結ぶのも立派な業務提携の方法です。あなたの動物病院のノウハウを広く知ってもらいたいという方にも、独立のサポートはおすすめです。
IT企業との業務提携
オンライン予約や電子カルテの導入など、動物病院でもDX化が著しく進んでいますが、知見がなく、何をどのように導入すべきかわからない方も少なくありません。そのような動物病院ではITコンサルに入ってもらい、業務の効率化や経営のスリム化を図ると効果的です。ITへの知識が豊富で、動物病院との提携実績のある企業であれば安心して提携できます。実際にIT企業と提携して、業務の効率化を図っている動物病院は少なくありません。
業務提携のメリットとデメリット
2020年に花王とライオンが協働し、リサイクル実証実験を開始したニュースは大きな話題を呼びました。また、大手ビール会社のアサヒやキリン、サントリー、サッポロはビールの共同配送を開始しています。このように同業他社と手を組んで、ひとつの事業に取り組んでいる事例は決して珍しくありません。
業務提携のメリットとしては、限られた経営資源を提供しあうことで、自分の動物病院だけではできない、大きな事業に取り組める点が挙げられます。また、他社のノウハウを学んだり、人脈の幅を広げたりすることで販路の拡大も期待できるでしょう。価格競争に陥って、相場よりも低い価格でサービスを提供することもなくなります。
このようにメリットが多い業務提携ですが、決してデメリットがないわけではありません。こちらが相手のノウハウを習得できる一方で、自分の動物病院の手の内を相手に明かすことでノウハウをマネされるおそれがあります。自分の動物病院内だけであれば難なくできていた商品・サービスの管理も、2つの医院をまたぐことで煩雑になるかもしれません。人間関係のトラブルも発生しがちです。
お互いがメリットを感じて、気持ちよく協業するためには、ライバルの選定から業務の進め方までを慎重に決めていく必要があります。そのコツについて見ていきましょう。
人脈を広げる大切さについては、以下の記事で触れていますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:業界外の人の目線も持って視野を広げよう
動物病院の業務提携の形態
業務提携の形態は大きく分けると、
- 生産提携
- 販売提携
- 技術提携
の3つです。
動物病院の提携としてもっとも取り組みやすいのは、やはり販売提携でしょう。自分の動物病院のオリジナル商品をライバルの動物病院に置いてもらったり、宣伝してもらったりすることで販路を拡大できるかもしれません。営業が得意ではない獣医師におすすめの方法です。また、他院の技術やノウハウを自院にも取り入れたい場合には、技術提携を結ぶことで売上が上がったり、作業効率が改善されたりするかもしれません。
協力者になるライバルの選び方
業務提携を成功させるためには、まずは提携の目的を定めて、協力者候補を慎重に選定すべきと考えます。これを誤ってしまうと、計画のすべてが失敗に終わってしまいます。
もしも「新しい診療サービスを開始したいけれど、自分の動物病院に必要な機器がない」ということであれば、その資源を有している動物病院を探して、紹介制度を提案してみると良いです。業務提携を交渉する際には、お互いにメリットがあると感じさせるのがポイントです。
もちろん、経営資源さえあればどのような動物病院であっても良い、というわけではありません。信頼できる動物病院かどうかも重要なポイントです。提携した動物病院で問題が発覚した場合、自分の動物病院の社会的信用にも関わるおそれがあります。「人気だから」「診療サービスが充実しているから」といった安易な理由でパートナーを決めないようにしましょう。
ライバルを意識するメリットについては、以下の記事で触れていますのでぜひ参考にしてください。
関連記事:「やるしかない状況」が経営者を成長させる
協力者への交渉と契約方法

「パートナーシップを結んでみたい」と思える動物病院を見つけたら、交渉をすることになります。このときには業務提携の目的や条件を、明確にこちらから持ち掛けなければなりません。このときには、「胡散臭い」「怪しい」と思われないように、説得力のある資料やビジョンが必要です。
双方が業務提携を承諾したら晴れてパートナーシップを結ぶことになりますが、どんなに親しい間柄であったとしても、必ず契約書を交わすようにしてください。提携期間や解除の条件はもちろん、第三者へのノウハウの流出を防ぐ秘密保持契約(NDA)も締結するに越したことはありません。
業務提携を成功させるためには
ライバルと手を結んで協力者になってもらったら終わり、というわけではありません。業務提携を成功させるためには、お互いが明確な目的をもち、密にコミュニケーションを取って達成度合いを確認していきます。うまくいかなかったときやモチベーションが下がってきたときのリスクヘッジも重要です。また、なあなあの関係は業務提携をした後にフィー配分や費用負担でもめることが多いため、書面で明確化しておきましょう。
限られたリソースでは実現不可能なことも、同業他社と手を結ぶことで達成しやすくなります。ライバルの存在を過剰に気にする必要もなくなり、これからの動物病院の発展に寄与できるかもしれません、気が合いそうなライバルがいる方は、一度業務提携を検討してみてはいかがでしょうか。
また、同業他社だけではなく間接競合を意識する大切さについても、一度ぜひ意識してみてください。以下の記事で触れています。
関連記事:同業他社だけではなく間接競合を意識して値付けをしよう